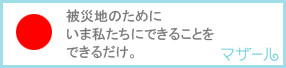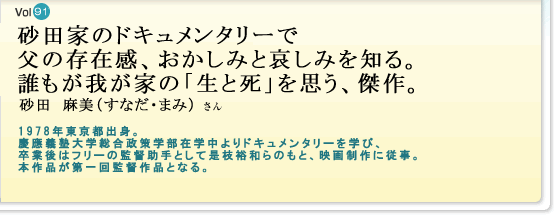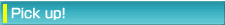
|
●『エンディングノート』
10月1日より、新宿ピカデリー他にて全国公開
(c) 2011「エンディングノート」製作委員会
*公式サイトはこちら
ガン告知後、最初に取り組んだのは“エンディングノート”と呼ばれるマニュアル作りでございます。自分の人生をきちんとデッサンしておかないと、残された家族は困るでしょうから・・・
家族の絆を「娘」が描いた、感動のエンターテインメント・ドキュメンタリー。
撮影・編集・監督 砂田麻美
製作・プロデューサー 是枝裕和
主題歌 ハナレグミ「天国さん」(SPEEDSTAR RECORDS) 音楽 ハナレグミ
製作 バンダイビジュアル
配給・宣伝 ビターズ・エンド
(2011年/日本/カラー/デジタル/90分)
|
|
|

|
|
退職後、会社命の父が手がけた「死に至るまでの段取り」
|

|
| |
| 1964年(昭和39年)、丸の内に本社を置く化学メーカーへ入社。一貫して営業畑を歩み、2007年に引退。 |
映画『エンディングノート』には、派手なイメージビジュアルはなく、いかにも営業マンらしい恰幅のよいお父さんがガハハと笑う写真が添えてある。映画の主人公はこの父・砂田知昭さん。彼を撮影した娘は、今回の作品を監督・編集も手がけた砂田麻美さん。実は当初、知り合いからリリースを頂いたのだが、映画のあらすじを読んでも正直なところ「ふーん。家族のドキュメンタリーか〜」というくらいで特別な感情は湧かなかった。けれども映画が始まって何分かで、すぐ砂田一家の一員になったような、映像の中に自分も介在している錯覚に陥り「他人事ではない世界」にスルスルと引き込まれた。
映像の舞台は2009年の東京。お葬式のシーンから始まった。そしてカメラは勤続40年の会社を退職する祝いの席で砂田知昭を捉える。熱血サラリーマンとして営業畑を歩んできた彼は、退職後やっと第二の人生を歩もうとしていた矢先、健康診断で胃ガンが発覚する。すでにステージ4まで進行した病魔を知り、右往左往するどころか、残された家族のため、人生総括のため、最後の一大プロジェクトとして「自らの死の段取り」と、その集大成ともいえる『エンディングノート』の作成に取り組む。そして半年後にやってきた最期に、死にゆく父が何を伝え、家族はどう寄り添ったか。……カメラは丁寧に、その様子を追う。淡々と、彼の心の声を娘(砂田麻美)がつぶやく手法は、父のキャラクター的おかしみを増幅させるだけでなく、冷静に家族の死を見つめる「もうひとつの目」として存在している。
|
高度経済成長期を過ごしてきた父を思う |
 |
| |
| 熱血営業マンとして高度経済成長期に会社を支え駆け抜けた「段取り命!」のサラリーマン・砂田知昭。若かりし頃の夫妻。
|
かつて高度経済成長期は私の父も、砂田監督の父上同様「仕事命」の人だった。でも、こんなふうに残す家族へ何かを伝える「段取り力」など兼ね備えてはいないし、そもそも人に伝えられるような人格者ではない。そういう意味で砂田監督は父上のことが大好きで、尊敬していたのではないかと思う。登場する砂田父があまりにも素晴らしい方なので、そんなお父さんを大好きでいたからこそ題材にできたのだろうな…とインタビュー第一声で砂田監督に話を振ると、意外な答えが返ってきた。
「反抗期は普通にありました。お父さんに関心を払わない時期というのかな。何かにつけて突っかかってみるとか…。その逆で言えば、小学3年生の頃が、父親っ子のピークでした。小3の時1年間日記を書く宿題があって、学年最後にその日記を立派な装丁で製本してくれたんですね。先日、本棚からそれを手に取って読んでみたら、ちょっと気持ちの悪いくらいお父さんの帰りを待っていた(笑)。それ以降は非常にフラットな関係性というか、べたべたした感じではなかったと思います。いずれにせよ、父だけでなく家族のことを客観的に見ている子どもでした」
例えば、それは93年にこっそり撮影した夫婦喧嘩も、子どもの目線で、ふすま越しに父母のやり取りを垣間見ている。どこの家庭でもあるシーンでありながら、砂田監督はカメラを片手に、じっとその様子をそのままの空気で捉えていた。なんと15歳にしてその目で捉えるセンスは光っていたことになる。
母方の祖父が写真館を営んでいる一方、父方の祖父もカメラが好きで当時は珍しい8mmカメラを持っていたり、父もテープの原材料を扱う仕事だったため、ビデオやカメラ自体が身近だったという。過去の希少な映像も効果的に映画の中でインサートされている。何十年も前のモノクロ写真や、砂田家の子どもたちの表情を8mm映像で捉え、それが一層、人の歴史に厚みを感じさせる。
|
予期せぬ形で父を世の中に出すことに |
 |
| |
| 熟年離婚の危機も乗り越え、これから第二の青春を謳歌…という矢先に胃ガンが発覚。 |
そもそも砂田監督がこの作品を撮ろうとしたきっかけは何だったのか。
「これは誰かから仕事として依頼されて撮り始めたのではなくて、ホームビデオの延長で、とにかく撮りたいから撮る…という欲求が始まりでした。映画作品にするつもりはなくて、父が亡くなってから誰かに見せることがあったとしても身内や知人だけで観るつもりでした。撮り始めてから父の病状が悪化して、私自身が辛くなり一度は撮ることをやめました。でも、しばらく撮らずにいた時に、友人に『本当に撮らなくていいの?』と言われ背中を押された気がして…やはり撮っておきたいと思い直しました。但し、自分が撮りたくない時、父が撮られたくない時は、撮影はしないでおこうというルールのもとで、続行しました」
自分も相手も苦しめるような撮影はしないルールを作って、被写体である父との距離感をほどよく保ちながら、カメラは静かにその姿を追っている。父がカメラに向かってかしこまって答えるような場面はほとんどない。どのシーンでも、そこに流れていたであろう日常が刻まれている。生活する姿がありのまま。そして、たくさんの父を捉えた膨大なテープが残った。それを一つの作品にしようと思った理由をこう語る。
「父を亡くして、これまであじわったことのない喪失感がありました。まるで自分と世界の間に薄い膜がはられたような、これまで見てきた世界が大きく変わってしまったような感覚。その気持ちをどう消化すればいいかわからないまま過ごす中で、自然にこれまで撮ったものをつなげて一つの作品としてみようという気持ちになりました」
これは親族を亡くした経験のある人は、少なからず理解できる気持ちだ。しかし砂田監督は娘としての気持ちの整理のためだけに作品にしたわけではない。父の死から得た最も大きな事は、「人の死は尊いものである」という意識。
「すべての人の死があって、私たちの生がある。作品を通じて届けたい強いメッセージはないけれど、死にゆく人に寄り添った映画でありたいと思うんです」
|
いい話より、おもしろい話のほうが伝わる |
 |
| |
| 幼い孫娘と戯れる時間が何よりも楽しみ。カメラを回していても無防備なのが伝わってくる。 |
この「エンディングノート」は人間が命を終えるまでを追っていると同時に、生きているものが死にゆく者を気持ちよく天国へ送りだす作法を知れる。映画のなかで、砂田監督の父上(父方の祖父)の場面がインサートされる箇所がある。地方の小さな田舎町で開業医をされ、やがて認知症を患った祖父は、来るはずもない患者さんを診察室で待ち続けている。かくしゃくとして頼りにされていたお医者様でさえ、老いには逆らえないし止められない。哀しいことだけれどちょっとおかしくもあり、たぶん生きるということはそういうことの繰り返し(祖父は10年ほど前に他界されている)。砂田監督は、そういう細かな描写も意識されたのだろう。
「いい話は、家族の中で共有できればいい。作品としては、いい話よりおもしろい話のほうが大事なことが伝わると考えました。ですから、ガンの闘病記とか、父へのメッセージ満載な物語を作ろうとかいうねらいはまったくなくて、結果的にたくさんの方にユーモアを感じとってもらえる作品になったのだと思います」
お涙頂戴なドキュメンタリーではなく、何か人として大事なことを手渡される作品。そして人の死に様は、生き様の延長にある。どんな人にとっても平等な「死」という事柄を受け入れる先に、残されたものは希望を見出したい。それが生かされた私たちの、命のつむぎ方なのかもしれない。
お会いしてみると砂田監督はとても小柄でかわいらしい人だ。たぶん、その容姿もあって「撮影という威圧感」なく、カメラを携えていても人を無防備にさせてしまうのだろう。大学の頃から、映画制作のサークルでその撮影手腕を発揮し、さまざまな友人に「私をこんなにいつ撮っていたの?」というほど仲間の姿も自然にカメラで捉えてきた。一作目でこれだけおもしろい作品なので、次回作の構想があるかと尋ねると「いつか結婚式をテーマに撮りたい」と即答。ご自身にとっても、きっと楽しみな一大プロジェクトになるはずだ。
|
| 公開日:2011年9月2日 |
 |
|
 砂田監督のお話しされる日本語は、とても美しく、耳に心地よかったです。お育ちのよさって、その人が語る言葉に表れるものです。3人きょうだいの末っ子の砂田監督は、9歳上のお姉さん、7歳上のお兄さんよりも、ご両親の愛情を一心に受けてこられたのだろうなぁ…と感じました。日本の高度経済成長期、企業に勤める父親は誰もが忙しく、新聞記者だったうちの父はほとんど家に居ませんでした。デジカメなぞなかった時代、毎年の年賀状に、一眼レフで撮影した子どもの写真を載せて自慢気でした。カメラが身近なご家庭だった砂田監督のお宅も、「年賀状には気合いが入ってた」のだそう。普段あんまり一緒にいられなかった父の罪滅ぼしだったのか、単なる成長記録だったのか(笑)。思春期を迎えた中学生の頃は、もう写真を撮らせなくなりましたが、もっと残しておけばよかったなぁ…。左の写真は、パンダちゃん初来日直前のお正月。左は3つ上の姉、右が私です。かわいい姉妹だったんですよ、当時は…。とほほ。
(マザールあべみちこ) 砂田監督のお話しされる日本語は、とても美しく、耳に心地よかったです。お育ちのよさって、その人が語る言葉に表れるものです。3人きょうだいの末っ子の砂田監督は、9歳上のお姉さん、7歳上のお兄さんよりも、ご両親の愛情を一心に受けてこられたのだろうなぁ…と感じました。日本の高度経済成長期、企業に勤める父親は誰もが忙しく、新聞記者だったうちの父はほとんど家に居ませんでした。デジカメなぞなかった時代、毎年の年賀状に、一眼レフで撮影した子どもの写真を載せて自慢気でした。カメラが身近なご家庭だった砂田監督のお宅も、「年賀状には気合いが入ってた」のだそう。普段あんまり一緒にいられなかった父の罪滅ぼしだったのか、単なる成長記録だったのか(笑)。思春期を迎えた中学生の頃は、もう写真を撮らせなくなりましたが、もっと残しておけばよかったなぁ…。左の写真は、パンダちゃん初来日直前のお正月。左は3つ上の姉、右が私です。かわいい姉妹だったんですよ、当時は…。とほほ。
(マザールあべみちこ)
|
|